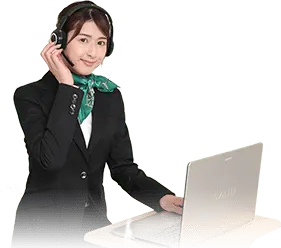実家じまいはどうする?
負動産にしないための手順と費用
目次
- 実家じまいの4つの方法
- 建物ごと売却する
- 更地にして売却する
- 不動産会社に買い取ってもらう
- 賃貸やパーキングとして活用する
- 実家じまいの手順
- ① 親族で話し合う
- ② 家の中を片付ける
- ③ 不動産会社に相談する
- ④ 実家を手放す
- 実家じまいにかかる費用
- 片付けにかかる費用
- 不動産売却にかかる費用
- 建物の解体にかかる費用
- 実家じまいで活用できる補助金・控除制度
- ① 空き家解体費用の補助金(自治体)
- ② 空き家バンク制度と関連補助(自治体)
- ③ 相続空き家の3,000万円特別控除(国の制度)
- 実家じまいで起こりうるトラブルとは?
- 親族で話し合いがまとまらない
- 売却が難しい物件だった
- 権利書がない
- 片付け費用が想像以上にかかる
- カンクリ不動産で実家じまいをサポートした事例
- 事例① 余命わずかな親の実家を、生前に売却してトラブル回避
- 事例② 東京からの遠隔対応で、実家の片付けと売却がスムーズに完了
- 事例③ 農地と実家をまとめて処分。複雑な手続きも一括対応
- 実家じまいせずに空き家のまま放置するのはNG!
- 維持管理費がかかる
- 特定空き家に指定される可能性がある
- 建物の価値が下がる
- 近隣住民とのトラブルの原因となる
- 実家じまいはカンクリ不動産に丸投げできる!
- 荷物の片付けから不動産買取までワンストップで依頼可能
- 完全自社買取だから仲介手数料無料
- 最短1日で現金化
- 法的手続きもサポート
- 親族で話し合い納得のいく実家じまいを実現しよう!
親が亡くなったり、施設に入ったりして、誰も住まなくなった実家。
「片づけないといけないのはわかってるけれど、何から始めたらいいか分からない」と、お困りの方も多いのではないでしょうか。
「実家じまい」とは、誰も住まなくなった実家を片づけ、手放す一連のプロセスのこと。
決断のタイミングは、親が施設に入る・相続が発生する・実家を維持できなくなるなど、人によってさまざまです。
忙しさや心理的なハードルから後回しにされがちですが、実家を空き家のまま放置しておくと、税金・管理・老朽化・近隣トラブルなど、思わぬリスクを抱えることにもなりかねません。
この記事では、実家じまいの方法や手順、費用や補助金、よくあるトラブル事例まで、分かりやすく解説します。
「まずは何をすればいいのか」を知るところから、一緒に始めてみませんか?
実家じまいの4つの方法
実家じまいを考えるとき、まず決める必要があるのが「実家をどう扱うか」という方針です。
状況や優先順位によって選択肢はさまざまですが、代表的な方法をご紹介します。
建物ごと売却する
建物と土地をセットで売却する方法です。築年数や状態によっては、買い手が見つかりにくいこともありますが、リフォーム前提で購入する人もいるため、まずは査定に出してみましょう。
更地にして売却する
建物の老朽化が進んでいたり、価値がないと判断されたりする場合は、解体して更地にしてから売却する方法もあります。
ただし、解体費用は自己負担になることが多いため、事前に費用の見積もりを依頼しましょう。
不動産会社に買い取ってもらう
「早く現金化したい」「自力で売却するのが大変」といった場合は、不動産会社による直接買取という選択肢もあります。
仲介とは違ってすぐに売却が決まる安心感があり、家の中に荷物が残っていても対応してくれる業者もあります。
賃貸やパーキングとして活用する
立地や建物の状態が良ければ、売却せずに貸し出すのもひとつの方法です。建物を取り壊し、駐車場にして貸し出す方法もあります。
ただし、空室リスクや修繕・管理の手間が発生するため、賃貸経営などの運用にかかるコストや責任も踏まえて慎重に判断しましょう。
実家じまいの手順
実家じまいをスムーズに進めるには、順を追って段階的に整理することが大切です。
「何から手をつければいいのか分からない」という方のために、基本的な進め方を4つのステップに分けて解説します。
① 親族で話し合う
実家じまいの第一歩は、親族間でしっかりと話し合うことです。とくに親がまだ存命の場合は、必ず本人の意向を確認し、尊重しましょう。
「処分に同意しているか」「今後どこで暮らすのか」といった具体的な確認が必要です。
あわせて、この段階で以下の事項を話し合っておくと、後のトラブルを防げます。
- 実家をどう処分するか(建物ごと売るのか、更地にして売るのか等)
- 誰が相続するか、遺産の分配方法は?
- 相続登記の手続きは誰が行うか
実家が不動産という「財産」である以上、相続や登記の整理は避けて通れません。
2024年から相続登記は義務化されており、放置すると罰則が科されるケースもあります。
② 家の中を片付ける
処分の方向性が決まったら、次は実家の中に残された荷物や遺品の整理です。
長年暮らしていた家ほど物が多く、家族だけで対応しようとすると想像以上に時間も労力もかかります。
「どこから手をつければいいのか分からない…」という場合は、遺品整理業者や不用品回収業者への相談も選択肢のひとつとして有効です。
カンクリ不動産では、片付けを含めた実家じまいを一括でサポートしています。
荷物がそのまま残っていてもOK。現状のままでも買取可能なので、遠方からの手配や立ち会いが難しい方にもご安心いただけます。
③ 不動産会社に相談する
実家の片付けがある程度進んだら、不動産会社に査定を依頼しましょう。
不動産の価値を知ることで、売却か賃貸か、あるいは買取を選ぶかの判断材料になります。
また、物件の状態や立地によっては「仲介で買い手を探すより、買取の方が早く確実」という場合もあります。
とくに売却を急ぎたい・煩雑なやりとりを避けたい場合は、買取専門業者への相談がおすすめです。
④ 実家を手放す
価格や条件に納得できたら、いよいよ売却・引き渡しへと進みます。
書類の準備や名義変更、税務手続きなど、やるべきことは多岐にわたりますが、経験豊富な業者であれば、法的手続きまでサポートしてくれる場合もあります。
「思い出が詰まった家を手放す」というのは、感情的にも簡単ではありません。
だからこそ、信頼できる相手に託すことが、納得できる実家じまいへとつながります。
実家じまいにかかる費用
実家じまいにかかる費用は、「何をするか」によって大きく変わります。
ここでは、代表的な費用項目とおおよその相場をご紹介します。
「全部でいくらかかるのか不安…」という方は、まずどの作業が必要かを整理してみましょう。
片付けにかかる費用
家の中に残された家財道具や不用品を処分するためには、ある程度の費用がかかります。
自力で片付けるなら、ゴミ処理費や車両レンタル費用程度で済みますが、遺品整理業者や不用品回収業者に依頼するケースが一般的です。
費用相場の目安
- ワンルーム:約3万〜10万円前後
- 一戸建て(3LDK〜4LDK):約10万〜30万円前後
業者に頼む際の費用は、家の広さ・荷物の量、階数・搬出経路、分別の有無などによって変動します。
カンクリ不動産では、実家の片付けと買取を一括で対応
「片付けてから相談」ではなく、「片付いていなくてもOK」。忙しい方や遠方の方にもご好評いただいております。
不動産売却にかかる費用
実家を売却する際には、物件の売値からは見えづらい諸費用や税金が発生します。
とくに見落とされがちなのが、以下の項目です。
- 譲渡所得税(売却益が出た場合に発生)
- 登記費用(所有権移転や相続登記、抵当権抹消登記など)
- 仲介手数料(不動産仲介で売却した場合)
- 測量・境界確定費用(境界があいまいな場合。解体時に行うケースもあり)
- 印紙税(売却額により1,000円~数万円)
- 司法書士への報酬(登記や書類作成時)
相続後の売却には、様々な手続きや書類作成が必要です。
放置していると税制優遇を受けられなくなったり、余計な手間や費用が発生したりといったケースもあるため、早めに司法書士や不動産会社等の専門家へ相談することをおすすめします。
建物の解体にかかる費用
古い家や空き家のままでは買い手が見つからない、あるいは土地だけを売却したい場合は、建物を解体する必要があります。
解体費用は、構造や立地、広さによって大きく異なります。
木造一戸建て(30坪程度):約80万〜120万円
※RC造などの場合はさらに高額になるケースも
また、解体時には以下のような付帯費用がかかることもあります。
● 廃材の処理費用
● 地中埋設物の撤去
● 隣地との境界確定費用
なお、建物を解体して更地にすると、固定資産税が高くなることがあるので注意が必要です。
家が建っている土地は、税金が安くなる「住宅用地の特例」が使えますが、建物を壊して更地にしてしまうと、この特例が使えなくなり、固定資産税が最大で6倍近くに跳ね上がることもあります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者がその年の税金を納めなくてはなりません。
そのため、「解体してから売る」のが良いか、「建物付きのまま売る」のが良いかは、売却のタイミングや見込みによって判断しましょう。
実家じまいで活用できる補助金・控除制度
実家じまいでは、自治体や国が提供する補助金・控除制度を活用することで、費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。
ここでは、とくに実用的な制度を3つご紹介します。
① 空き家解体費用の補助金(自治体)
多くの市区町村では、老朽化した空き家の解体に対する補助金制度があります。
補助率:解体費用の約1/2が相場
補助上限:50〜100万円程度が一般的
対象条件
● 築年数(例:30年以上)
● 空き家期間(例:5年以上)
※倒壊の恐れなどの要件あり
例:京都市は解体費用の1/3を補助し、上限は60万円(+隣地整理で加算も)
空き家に関する補助金制度は、多くの自治体で実施されています。実施内容は大きく異なるため、「○○市 空き家 補助金」などと検索して居住地の市区町村ホームページで要件を確認しましょう。
② 空き家バンク制度と関連補助(自治体)
自治体によっては、「空き家バンク」という仕組みを使って、実家を売ったり貸したりする人をサポートしています。
空き家バンクとは、空き家を売りたい人と、住みたい人をマッチングするための自治体の登録制度です。
この制度を使うと、次のような費用が補助される場合があります。
- 家の中に残った荷物の片付け費用
- リフォーム・修繕の費用
他にも、登録すれば住宅ローンの利子を一部負担してくれる地域もあります。
ただし、補助の内容や対象となる条件は自治体によって異なるため、実家のある市区町村のホームページで必ず確認してみましょう。
③ 相続空き家の3,000万円特別控除(国の制度)
相続した実家を売却した場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円控除する特例があります。
例えば、相続した一戸建てを100万円かけて解体し、1,000万円で売却した場合、条件を満たしていれば約170万円もの譲渡所得税を節税できるケースもあります。(税率は所有期間等により異なる。)
対象となる不動産や主な条件は次のとおりです。
- 亡くなった所有者(被相続人)が一人で住んでいた家(相続開始直前に居住しており、同居人がいないこと)
- 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅
- 解体または耐震改修のうえで売却(買主が耐震改修を行う場合も可)
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却
- 譲渡価格が1億円以下
- 確定申告でこの特例を適用する旨を申告している
かなりの節税効果があるため、相続後すぐの売却計画には有効です。
ただし、制度の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までとなっています。
実家じまいで起こりうるトラブルとは?
実家じまいは、思い出の整理だけでなく、不動産・相続・法律の問題が絡む「手続きの山」でもあります。
ここでは、実際によくあるトラブルの例を紹介します。事前に知っておくだけでも、同じ失敗を防ぐ助けになるでしょう。
親族で話し合いがまとまらない
実家じまいを進めようとしても、親や兄弟、相続人それぞれの意見が食い違い、話し合いがまとまらないこともありがちです。「売りたい」「残しておきたい」「住む予定がある」と立場が違えば、当然意見も分かれます。
また、実家が遺産分割の対象となる場合、以下のような相続トラブルに発展することもあります。
- 「長男だから家は自分が相続すべき」と主張し、他の相続人と衝突
- 誰がどこまで財産管理に関与したかをめぐって感情的な争いに
- 亡くなった親の介護をめぐり、「貢献度に見合った取り分が欲しい」と揉める
相続人同士の対立がエスカレートすると、実家じまい以前に話し合いすら前に進まない事態になりかねません。
こうした場合は、早い段階で第三者の専門家(司法書士や弁護士など)を間に入れると、感情的なもつれを避けやすくなります。
売却が難しい物件だった
実家じまいで最も多いトラブルの一つが、「売ろうとしても買い手がつかない」というケースです。
とくに次のような物件は、なかなか売却が進まない傾向があります。
- 駅から遠い、交通の便が悪い
- 築年数が古く、建物の価値がほぼゼロ
- 道が狭くて再建築が難しい「再建築不可物件」
- 地方や山間部の人口が減っているエリア
売れずに固定資産税だけが毎年かかり続けたり、ようやく売れても当初の希望より大幅に値下げしたりと、思うように売却できないケースは珍しくありません。
さらに、売却できずに相続税の納付期限(原則10ヶ月)を迎えると、「お金はないのに税金だけかかる」状態になってしまうことも。
こうしたリスクを避けるためにも、早めに専門業者へ相談し、売却の可能性や買取の選択肢を確認しておきましょう。
権利書がない
実家を売却したくても「権利証(登記済証)」が見つからず、手続きがストップしてしまうケースがあります。
権利証とは、「この不動産は自分のものです」と証明する重要な書類。売買・相続・担保などの際に必要になります。
親が保管していたまま亡くなったり、引越しの際に紛失していたりと、実家にまつわる書類は行方不明になりがちです。
もし権利証が見つからない場合でも、「本人確認情報」などを用いて再手続きは可能ですが、時間と費用が余計にかかるため注意が必要です。
相続登記や売却を考えるなら、早めに登記状況を確認し、必要書類をそろえておくことをおすすめします。
片付け費用が想像以上にかかる
実家じまいで想定外に負担となるのが、遺品整理や不用品の片付けにかかる手間と費用です。
とくに高齢の方が長年暮らしていた家では、生活用品や思い出の品が大量に残っており、物量が通常より多くなりがちです。モノがあふれてゴミ屋敷のような状態になっているケースもあり、自力で片付けるには相当な時間と体力を要します。
業者に依頼すると、間取りや荷物の量によっては30万円以上の費用がかかることも。
まずはできる範囲で自分たちで片付けつつ、複数の業者に見積もりをとり、条件の合うところに依頼するのがおすすめです。
カンクリ不動産で実家じまいをサポートした事例
実家じまいには、それぞれの家庭の事情があります。「遠方から片づけに行けない」「農地も一緒に処分したい」など、一般的な不動産会社では対応しきれないケースも少なくありません。
ここでは、カンクリ不動産が実際に対応した3つの事例をご紹介します。
ご自身の状況と重ねながら、「こんな相談もできるんだ」と参考にしてみてください。
事例① 余命わずかな親の実家を、生前に売却してトラブル回避

ご依頼主は、末期がんで入院中の親をもつ息子さん。医師から「余命1ヶ月」と告げられたことが、実家じまいを考えたきっかけです。
不動産のまま相続すると、他の相続人との遺産分割が複雑になることや、相続人同士だけで話し合うとトラブルになるかもしれないことを懸念されていました。
そのため、親が存命のうちに意向を確認し、実家を売却する判断をしたいとのことでした。
また、すでにかかっている入院費や付き添いの交通費などを考えると、 親が生きているうちに現金化しておきたいという思いがあったそうです。
親御さんには余命を告げていなかったものの、幸い意思疎通が可能な状態だったため、家族全員で話し合い、売却の意向を確認。
結果、ご契約からわずか1週間で売却・決済まで完了し、現金化によって円滑な相続にもつながりました。
相続後ではなく「生前に売却する」という選択が、経済的にも心理的にも大きな負担軽減となったケースです。
事例② 東京からの遠隔対応で、実家の片付けと売却がスムーズに完了

ご依頼主は、東京で暮らすご兄妹。京都の実家で一人暮らしをしていた80代のお父様と同居することになり、空き家となる実家の整理と売却についてご相談をいただきました。
実家は、1階の一部がテナントで、住居部分とあわせて約130㎡と広く、30年以上住まれていたため荷物の量も相当なものでした。
しかし、東京から何度も往復して片付けるのは現実的ではなく、築年数も古いため、すぐに買い手が見つかるかどうかも不安だったそうです。
また、複数の仲介業者に相談する中で、しつこい営業や強引な対応に疲れてしまったとのこと。
そんな折、近所の方からカンクリ不動産を紹介され、「実家整理から売却まで一括で任せられる」と知り、早期売却を希望してご契約いただきました。
カンクリ不動産では、荷物が残ったままの状態でも対応可能。遠方にお住まいの方でも、無理なく実家じまいを進められます。
事例③ 農地と実家をまとめて処分。複雑な手続きも一括対応

ご相談いただいたのは、地方にある実家と農地を相続されたお客様。一括で手放したいというご希望でした。
しかし、農地の売却には法律上の制限があります。原則として農地は、農家同士でしか売却できず、一般の不動産市場ではほとんど取引ができません。
「農地転用」と呼ばれる手続きを行えば売却の可能性は広がるものの、専門的な書類作成や許可申請が必要で、一般の仲介業者では対応できる業者が限られているのが現状です。
ご依頼者さまも複数の不動産業者に相談したものの、「対応できない」と断られ続け、困っていたところで売却が困難な訳あり物件を専門的に扱っているカンクリ不動産にご相談くださいました。
当社が提携する土地家屋調査士・司法書士などの専門家をご紹介し、農地転用に必要な整地作業や書類準備もトータルでサポート。
最終的には、農地とご実家をまとめて当社で買取させていただきました。
当社では、農地や訳あり物件の取り扱いにも豊富な実績があります。
田舎の実家や、畑・山林など、一般の業者では敬遠されがちな案件でも、柔軟に対応できる体制が整っています。
実家じまいせずに空き家のまま放置するのはNG!
「まだ時間があるから」「とりあえず保留で……」と、実家じまいを先延ばしにしていませんか?
空き家を放置しておくと、税金・劣化・近隣トラブルなどが振りかかるリスクがあります。
親がまだ元気なうちに、できる範囲から少しずつ整理を進めておくと、将来的な負担を大きく減らせます。
ここでは、実家を空き家のまま放置することで起こりうる主なデメリットを4つご紹介します。
維持管理費がかかる
空き家であっても、所有しているだけで固定資産税や都市計画税が毎年かかります。
使っていない実家に対して出費が続くと、精神的にも金銭的にも負担になりがちです。
さらに、建物の掃除や修繕、庭木の手入れなどの維持管理費も発生します。
管理のために遠方から通う場合、交通費もかさんでしまいます。
特定空き家に指定される可能性がある
管理が不十分な空き家は、自治体から「特定空き家」とみなされる可能性があります。
特定空き家に指定されると、住宅用地の特例(固定資産税の軽減措置)が解除され、税額が最大で6倍近くまで跳ね上がることもあります。
加えて、行政から指導・勧告・命令が出るケースもあり、最悪の場合は強制的に解体されることも。
「使わないからそのまま」では済まされない時代になっているのです。
建物の価値が下がる
住んでいない家は、時間が経つほどに建物の傷みが進み、資産価値も低下します。
湿気やカビ、外壁の劣化、害虫被害などは、短期間でも驚くほど進行します。
とくに売却を考えている場合、空き家期間が長引くほど「売りづらい物件」となり、価格交渉で大幅に下げられることもあるので注意しましょう。
近隣住民とのトラブルの原因となる
放置された空き家は、見た目の印象だけでなく、実害にもつながるリスクがあります。
● 異臭・ゴミの不法投棄
● 枯れ草・落ち葉による小規模火災
● 害獣や害虫の発生
● 空き巣や不審者の侵入
こうした問題は、近隣トラブルや自治会からの苦情につながり、思わぬ人間関係のストレスを生みかねません。
実家じまいはカンクリ不動産に丸投げできる!

「片付けも、売却も、手続きも…全部自分でやるなんて無理!」
そんな声にお応えできるのが、カンクリ不動産の実家じまいサポートです。
当社では、実家じまいに関わる作業をワンストップで対応。荷物が残った状態でも問題ありません。築年数が古くても、訳あり物件でも対応可能です。
全国47都道府県に対応しており、遠方からのご相談も多数いただいています。
そんなカンクリ不動産の特長を5つに分けてご紹介します
荷物の片付けから不動産買取までワンストップで依頼可能
カンクリ不動産では、遺品整理・不用品の処分など現地の片付けサポートはもちろん、現状有姿での買取にも対応しています。空き家に荷物が残っている状態でも問題なく、そのまま売却できます。片付けやリフォームをする必要はありません。
「時間がない」「遠方に住んでいて片付けに行けない」「どこから手をつければいいか分からない」という方も、遠隔で現場をそのままお任せいただけます。
他社で「条件が合わない」と断られた物件でも、まずは一度ご相談ください。
完全自社買取だから仲介手数料無料
当社では、買取から販売までをすべて自社で対応しているため、仲介手数料などの余計な費用がかかりません。
また、物件ごとの事情や地域性を踏まえた活用ノウハウを活かし、建築部門によるリフォームも社内で対応できるため、物件の価値を引き上げて査定額に反映いたします。
最短1日で現金化
カンクリ不動産は、買い手を探す仲介業者ではなく、自社で直接買い取る買取業者です。
そのため、「なかなか売れない」「買い手がつかない」といった心配がなく、最短1日で売却・現金化が可能です。
早く現金が必要な方、相続税の納付が迫っている方にも、多くご利用いただいています。
法的手続きもサポート
実家じまいでは、売却だけでなく、相続登記や名義変更などの法的手続きも必要になります。
カンクリ不動産では、提携している司法書士や土地家屋調査士などの専門家をご紹介し、煩雑な手続きをしっかりサポート。
法律に関する知識がなくても、安心して進められる体制を整えています。
親族で話し合い納得のいく実家じまいを実現しよう!
実家じまいは、思い出や家族の歴史に向き合う大きな節目でもあります。
片付けや売却、相続手続きなどやるべきことは多く、後回しにしたくなる気持ちも当然あるでしょう。
しかし放置してしまえば、費用や手間だけでなく、思わぬトラブルにつながることもあります。
だからこそ、親族で話し合い、納得のいくかたちで進めていくことが大切です。
カンクリ不動産では、片付けから買取、法的手続きまで、実家じまいを一括でサポートしています。
片付いていなくても、遠方でも、法律のことがわからなくても大丈夫。
まずは「ちょっと聞いてみる」くらいの気持ちで、お気軽にご相談ください。
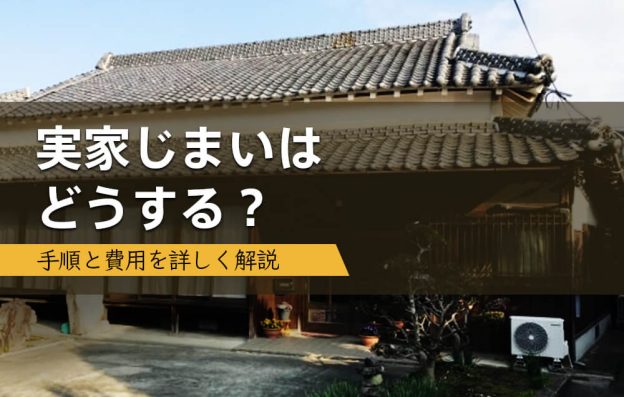

カンクリ不動産 代表 亀澤 範行さん監修