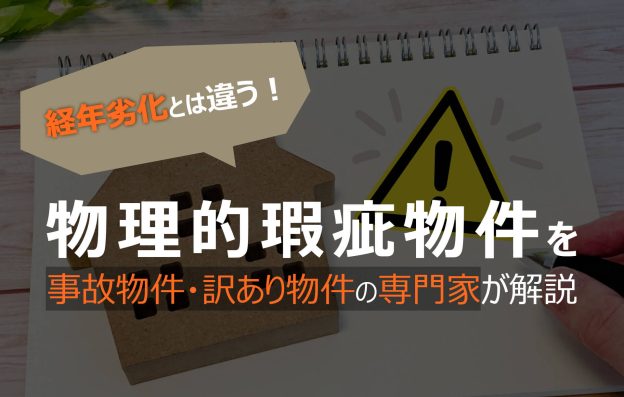物理的瑕疵物件とは?経年劣化と間違われやすい
不動産の欠陥を専門家が解説
目次
不動産業界で事故物件は「瑕疵物件」と呼ばれ、瑕疵の種類によって4つに分類されます。今回はそのうちのひとつである物理的瑕疵について、事例とともに分かりやすく解説します。
不動産の物理的瑕疵とは
物理的瑕疵(ぶつりてきかし)とは、不動産の構造や設備に生じる物理的な問題点です。大きく分けて、「建物の瑕疵」と「土地の瑕疵」の2種類が存在します。
建物の瑕疵とは、物件自体に存在する物理的な欠陥や損傷を指し、建物の安全性・機能性・快適性に影響を及ぼします。
[建物の瑕疵の例]
シロアリ被害、雨漏り、壁のひび割れ、床の傾斜、基礎の不均一な沈下、電気配線の誤り、水道管の漏れ、耐震強度の不足、アスベスト含有建材の使用など。
一方で土地の瑕疵とは、土地自体に存在する問題点や欠陥のことです。土地の利用価値や建築の安全性に影響を及ぼし、場合によっては法的な制限や追加の工事費用が必要となります。
[土地の瑕疵の例]
化学物質による土壌汚染、不発弾や井戸など地中障害物の存在、自然災害による地形の変化、地盤沈下など。
不動産取引では、これらの物理的瑕疵は不動産の価値減少や売買契約に影響を与えるため、事前の調査と適切な開示が重要です。
物理的瑕疵物件に発生する告知義務
物理的瑕疵がある物件を賃貸・売買契約する際には、取引相手に告知する義務があります。この告知義務を怠ると、契約が不適合とみなされ、訴訟に発展する恐れがあります。トラブル防止のためにも、「隠れた瑕疵」も含め、不動産に関する重要な情報は事前に開示しましょう。
老朽化や経年劣化は契約不適合責任の対象になる?
建物の築年数に伴う老朽化や経年劣化は、一般的に物理的瑕疵とは見なされません。ただし過去の判例によると、建物の築年数と照らし合わせて、「その性能や品質が期待される水準を満たしているか」が、契約不適合責任の判断基準となります。
たとえば、築38年のマンションで窓枠などから雨漏りが発生した事例(東京地裁平成26年1月15日)では、以下の点から瑕疵担保責任が否定されています。
- 購入時に築38年の物件であることが説明されており、買主も経年にともなう損耗などを承知して購入している
- 築年数が長く経過したマンションでは、雨漏りの原因となる建物のひび割れが発生することも一般的にあり得る
- 建物全体や窓、アルミサッシなどの性能について、契約上特段の合意はなされていなかった
また、契約書に特約を設けて、老朽化や経年劣化があることを了解した上で契約を進めるケースも存在します。
実際にあった物理的瑕疵の裁判事例

瑕疵物件を売買・賃貸する際には、告知義務が定められています。告知をせず取引を行った場合、売主(貸主)は告知義務違反と契約不適合責任を問われ、損害賠償請求を命じられる可能性があります。具体的な裁判例を参照しながら、この問題を深掘りしていきます。
購入住戸のルーフバルコニーに、上階からバルコニーの手摺の一部が落下
買主が購入した新築マンションのルーフバルコニーに、上階で使用されていたルーフバルコニーのてすりが落下したという事例です(※東京地方裁判所平成25年3月11日判決)。
買主は物件引き渡し後、バルコニーに長さ約1メートルの棒が落ちているのを発見し、施工会社の社員に調査を依頼しました。調査により、上の階のバルコニーに設置されたアルミ手すりの縦格子部材だと判明。
手すりの落下により、ルーフバルコニーに設置したエアコン室外機の一部がへこんでしまう事故も発生しています。また、買主のバルコニーに落ちる途中、別の部屋にも一度手すりが落下。その部屋ではコンクリートで造成した面台部分に傷がついてしまいました。
この件では、ルーフバルコニーは共有部分ではあるものの、購入者が専用使用権を有する「物件売買の目的物」と判断されました。そして安全性を欠いたものであり、売主が契約不適合責任を負うべき物理的瑕疵として認められています。
まとめ
ご紹介した事例のように、物理的瑕疵は売主が告知義務を怠ると、訴訟に発展するリスクがあります。ただし中古住宅では、経年劣化による損傷は物理的瑕疵とみなされにくい傾向にあります。そのためオーナー自身が瑕疵だと分からず、経年劣化と思い込んで取引してしまうケースも。
また、建築当時は一般的に使用されていた建材(アスベスト含有材など)が使用禁止になり、重大な健康リスクをはらむ瑕疵物件化することも珍しくありません。
不動産取引の際には、売主は物件について正確に把握し、責任を持って売買する必要があります。
物理的瑕疵物件の売却に困ったら訳あり物件買取専門業者のカンクリ不動産へ

物理的瑕疵か経年劣化かの判断に迷い売却に困った際は、ぜひカンクリ不動産へご相談ください。
カンクリ不動産は多数の実績をもつ、訳あり物件専門の不動産業者です。売主様から直接買取り、リフォーム、販売までをワンストップで行う専門業者として、多くの物件を再生し、新たな価値を創出してきました。
物理的瑕疵と見なされる部分には修繕やリフォームを行い、販売へとつなげます。
売主様の契約不適合責任は一切問いません。
瑕疵物件の取り扱いにお困りの際は、カンクリ不動産までお気軽にご連絡ください。お客様の不動産のお悩みを解決するお手伝いをいたします。