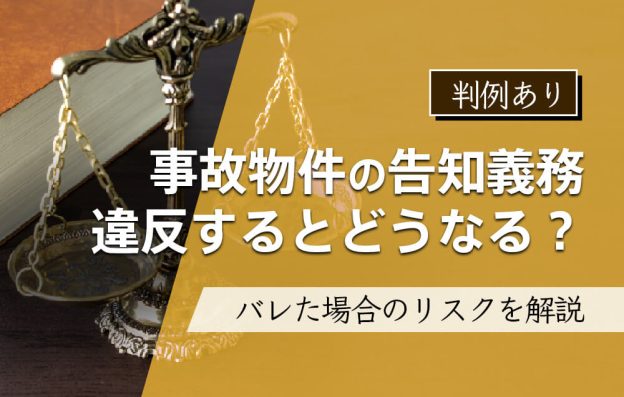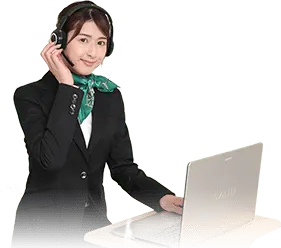【判例あり】事故物件の告知義務に違反するとどうなる?
バレた場合のリスク
目次
- 事故物件の告知義務違反で起こりうるリスク
- 事故物件の告知義務は売主や買主にもある
- 事故物件の告知義務違反で損害賠償を命じられた判例
- 賃貸物件の場合
- 売買物件の場合
- 事故物件の告知義務違反となる場合とは?
- 自殺や他殺など心理的抵抗が大きい死亡があった
- 特殊清掃が必要な事案だった
- 共用部分で死亡した
- 借主・買主から質問された
- ニュースで報道されるなど社会的影響が大きかった
- 事故物件の告知義務違反にならないのはどこまで?
- 自然死や不慮の事故による死亡
- 死の発覚から3年が経過している(賃貸の場合)
- 対象不動産の隣接住戸・通常使用しない共用部分での死亡
- 事故物件に一度住めば告知義務はなくなる?
- 事故物件で告知義務違反にならないために伝える内容とは?
- 1. 死因とその概要(自殺・他殺・自然死・事故死など)
- 2. 死亡があった場所(専有部・共用部・隣接住戸など)
- 3. 死亡からの経過年数
- 4. 特殊清掃の有無
- 5. 報道歴や周知性の有無
- 告知事項は書面で明確に残すのがベスト
- 事故物件の売却ならカンクリ不動産に相談【専門スタッフが対応】
- 事故物件の告知義務に関するよくある質問
- まとめ
所有物件で入居者が亡くなり、「事故物件になってしまった…」と悩んでいませんか?
借り手がつかなくなるかもしれない。売ろうとしても買い手も見つからないかも。できれば告知せずに済ませたい……そう思うのも無理はありません。
しかし、事故物件の告知義務を守らなかった場合、契約解除や高額な損害賠償を請求されるリスクがあります。
この記事では、実際の判例をもとに、告知義務違反をするとどうなるのか、どこまで告知が必要なのかをわかりやすく解説します。
事故物件をなるべく高く売りたいと検討中の方は下記の記事も参考にしてください。
関連記事>> 事故物件になると価格の下落はしかたない?価値を下げない対処法も解説
事故物件の告知義務違反で起こりうるリスク
✅買主・借主からの契約解除請求
✅ 契約金額の減額請求
✅ 損害賠償請求(価格差相当分、転居費用など)
✅ 信用失墜による他の取引への影響
事故物件であることを隠して契約を結ぶと、あとから契約解除や損害賠償の請求といった深刻なトラブルにつながりかねません。
悪質と判断されれば、慰謝料や弁護士費用まで請求されることも。
実際に事故物件であることを隠した結果、敷金返還になった例や、高額な賠償命令が下されたケースもあります。
事故物件に関する告知義務は、単なるモラルや配慮の問題ではなく、法律上の義務として定められています。宅地建物取引業法では、物件の購入・賃貸を検討する人の判断に大きな影響を与える事実を、意図的に隠したり、虚偽を伝えたりすることを禁止しています。
つまり、人の死に関する事案が「契約するかどうかの判断に影響する」と考えられる場合は、宅建業者にはそれを正しく伝える法的な義務があるのです。
事故物件の告知義務は売主や買主にもある
告知義務違反によるトラブルは、「事故物件だと告げたら契約が決まらないかもしれない」という不安から、つい告知を怠った場合に起こりがちです。しかし、「告知義務を知らなかった」「不動産会社が伝えると思った」では通用しません。
事故物件の告知義務は、宅地建物取引業者(不動産会社)だけでなく、売主・貸主自身にも課されます。とくに個人間の売買や自主管理の賃貸物件では、オーナー自らが説明責任を果たさなければならず、注意が必要です。
「事故物件であることを知っていながら黙っていた」場合、法律違反として責任を問われる可能性があります。売主・貸主にとっても重大なリスクであることを、正しく理解しておきましょう。
事故物件の告知義務違反で損害賠償を命じられた判例
告知義務違反が問題となった判例は複数ありますが、ここでは実際に賠償命令が出た2つのケースをご紹介します。
告知義務を怠れば賃貸・売買の両方でリスクが生じることを、具体的な金額とあわせて確認しておきましょう。
賃貸物件の場合
▶︎事案の概要(大阪高裁 平成26年9月18日判決)
入居の約1年5ヵ月前に室内で自殺があったことを、入居直後に知った借主が、告知を怠った貸主に対し退去費用などの損害賠償を請求した事案です。
▶︎裁判所の判断
裁判所は、自殺事故を知っていた貸主には信義則上、借主に対して事実を告げる義務があると判断。その義務を怠った貸主に対し、不法行為による損害賠償責任を認めました。
▶︎命じられた賠償額(合計 約104万円)
□ 賃料・礼金・保証料・引越費用・エアコン工事代など:約64万円
□ 弁護士費用:10万円
□ 慰謝料:30万円
貸主は控訴するも棄却され、貸主側の全面敗訴となりました。
売買物件の場合
▶︎事案の概要(東京地裁 平成20年4月28日判決)
賃貸収益目的でマンションを購入した買主が、過去に飛び降り自殺があったことを売主から告げられていなかったとして、告知義務違反を主張。売主である不動産業者に対し、7000万円の損害賠償を請求しました。
売買金額は1億7500万円。1階が事務所、2〜7階が住居の物件で、個人が不動産業者から購入しました。
▶︎裁判所の判断
売主は「事故を知らなかった」と主張したものの、以前の所有者との取引で事故の存在が示唆されていたことから、認識していたと判断。
事故から2年以上経過していたとはいえ、収益物件においては経済的不利益を及ぼす可能性があるため、買主に対して説明すべき義務があるとされました。
▶︎認定された損害額:2500万円
収益減・利回り低下などの経済的損害を具体的に算出した額が認められました。
賃貸・売買の、いずれの場合も「知っていながら黙っていた」ことが損害賠償につながっています。どちらも、告知義務を怠らなければ避けられたはずのトラブルでした。
事故物件の告知義務違反となる場合とは?
事故物件の告知義務に関して、国土交通省(以下、国交省)は2021年、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。これにより、「人の死」に関する告知義務の判断基準が定められました。
告知すべきかどうかは、「死因」や「発見状況」「社会的な影響の有無」など、さまざまな要素によって判断されます。
ここでは、貸主・売主が事故物件であることを「必ず告げなければならない」ケースを紹介します。
自殺や他殺など心理的抵抗が大きい死亡があった
物件内で自殺や、他殺など事件性のある死亡があった場合は、原則として告知義務が発生します。
さらに、告知義務の期間を過ぎていたとしても、社会的影響が大きいと判断される場合(例:報道で広く知られている等)は、「借主・買主が契約時に知るべき重要事項」として、引き続き告知義務が生じる可能性があります。
特殊清掃が必要な事案だった
たとえ自然死であっても、遺体の発見が遅れたことによって特殊清掃が行われた場合は、心理的抵抗があるとされ、告知義務が生じます。
ガイドラインでは、「特殊清掃を要する死」は社会通念上、借主・買主の判断に影響を与える可能性があるため、原則告知すべきとされています。
共用部分で死亡した
マンションなどの集合住宅で、エントランスや廊下などの共用部分で人が亡くなった場合も、一定の条件下では告知が必要です。
とくに、事件性がある場合や、共用部分の使用頻度が高い場合は、「借主・買主が日常的にその場所を利用する」ことを踏まえ、告知義務が発生します。
借主・買主から質問された
借主や買主から、対象物件における人の死にかかわる事件や事故について聞かれた場合、質問に正確に答える義務があります。
たとえガイドライン上で「告知しなくてもよい」とされるケースであっても、質問に対して事実を伏せることはできません。事実を隠したり、意図的に曖昧に答えたりすると、後にトラブルへ発展する恐れがあります。
ニュースで報道されるなど社会的影響が大きかった
事故や事件がニュースで大きく報道されたり、衝撃を与えるなどして周辺地域で記憶されていたりする場合は、ガイドライン上で告知する必要が無いとされるケースでも告知義務が生じる可能性があります。
たとえば以下のようなケースです。
- マスコミによる繰り返しの報道がなされた事件現場
- 著名人がマンションの屋上で亡くなったことで社会的関心が集まった自殺
- 地元住民の間で強い記憶や風評が残っている場合 など
事故物件の告知義務違反にならないのはどこまで?
事故物件に関する告知義務は、原則として「人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」と定められています。
しかし、「すべての死亡事案で必ず告知しなければならない」というものではありません。ガイドライン上、一定の条件下では告知義務が発生しないとされるケースもあります。
自然死や不慮の事故による死亡
体調の急変による病死・老衰などの自然死・不慮の事故死(転倒など)の場合、発見が早く、特殊清掃の必要がなかったケースでは、原則として告知義務はありません。
ただし、遺体の発見が遅れ、腐敗が進んだことによって特殊清掃が行われた場合は、心理的瑕疵とされ、告知が必要になります。
死の発覚から3年が経過している(賃貸の場合)
賃貸物件については、自殺や他殺、特殊清掃が必要な死亡であっても、発見から3年以上が経過していれば、原則として告知義務はないとされています。
対象不動産の隣接住戸・通常使用しない共用部分での死亡
マンションの隣の部屋や、住民が日常的に使用しない共用部分(屋上、機械室など)で人が亡くなった場合、対象物件の使用や生活に直接の影響を与えないと考えられるため、原則として告知義務はありません。
【ワンポイント💡】原則を満たしていても、告知義務が残る例外も!
たとえ死亡から3年以上が経過していたり、死亡場所が隣室や通常使用しない共用部分(屋上など)であったとしても、社会的影響が大きい事件・事故である場合には、例外的に告知義務があると判断されることがあります。
特に報道やSNS拡散により物件が特定されているケースでは、入居者・買主にとって重大な心理的瑕疵となるため、原則にとらわれず説明責任を果たすことが重要です。
事故物件に一度住めば告知義務はなくなる?
「誰かが一度住めば、もう事故物件として告知しなくていいのでは?」と考える人は少なくありません。以前は、そうした賃貸運用が暗黙のうちに行われていたケースもありました。
しかし、2021年に国交省がガイドラインを策定して以降、この考え方は否定されています。つまり、誰かが一度住んだからといって、告知義務が自動的に消えるわけではありません。
ガイドラインでは、賃貸契約の告知義務は概ね3年間は必要と示されており、3年以内であれば「一度別の入居者がいたかどうか」に関係なく、告知義務は発生します。
一方の売買契約では、明確な期限が示されていません。心理的瑕疵が買主の購入判断に影響を与えると考えられる限り、売主には告知義務があると判断される場合があるため、慎重な判断が必要です。
事故物件の告知義務期間についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事>> 事故物件「人の死の告知義務」は何年?心理的瑕疵はいつまで続くのか
事故物件で告知義務違反にならないために伝える内容とは?
告知義務違反を避けるには、「何を、どのように伝えるべきか」を正確に理解することが大切です。単に「人が亡くなった」という事実だけでなく、死因・場所・時期・清掃の有無・社会的影響などの詳細が告知の対象となります。
以下は、国交省のガイドラインや判例などをもとにした、伝えるべき主な内容の例です。
1. 死因とその概要(自殺・他殺・自然死・事故死など)
死因は、告知義務の有無を判断する重要なポイントです。事件性がある死亡(自殺・他殺など)は必ず告知の対象となります。
自然死や不慮の事故死でも、特殊清掃を要する場合は原則告知が必要です。
2. 死亡があった場所(専有部・共用部・隣接住戸など)
死亡場所が物件内の専有部(部屋の中)であるか、共用部分であるか、あるいは隣室・上下階かによっても告知の必要性は異なります。
専有部での死亡は基本的に告知が必要とされます。
3. 死亡からの経過年数
賃貸物件の場合、死亡の発覚から3年を経過していれば原則、告知義務は不要となります。
ただし、事件性のあるケースや社会的に注目された事案では、経過年数にかかわらず告知すべきとされる場合があります。
4. 特殊清掃の有無
遺体の腐敗による異臭・汚損があったかどうか、特殊清掃やリフォームが実施されたかは、借主・買主の判断に大きく影響するため、明示が求められます。
5. 報道歴や周知性の有無
TVや新聞、インターネットで事件が報じられている場合は、「社会的に知られている事実」として、心理的瑕疵の程度が高いとみなされ、告知の必要性が増します。
告知事項は書面で明確に残すのがベスト
事故物件の詳細を伝える際は、口頭だけで済ませず、重要事項説明書などの書面に記載することが大切です。
あとになって「言った・言わない」の争いになれば、契約自体が無効とされる可能性もあります。余計なトラブルを避けるためにも、契約時に記録に残すことが重要です。
【ワンポイント💡】告知義務違反にならないためには?
告知義務違反にならないためには、知っていることは正直に伝え、不動産会社と情報共有することです。
心理的瑕疵にあたるかわからないケースや、告知義務の範囲で悩んだら、弁護士や宅建士などの専門家に相談するのが安心です。
事故物件の売却ならカンクリ不動産に相談【専門スタッフが対応】

✅事故物件取扱い年間1000件超
✅他社で断られた物件もOK
✅匿名でのご相談も可能
事故物件は、「怖い」「縁起が悪い」といった心理的理由から敬遠されやすく、仲介で売り出しても、なかなか買い手が見つからないのが現実です。
中には「告知が面倒」「何年も売れ残るくらいなら、もう手放したい」と感じる人もいるでしょう。
そんなときに頼れるのが、事故物件の取り扱いに慣れた専門業者です。
カンクリ不動産では、事故物件や訳あり物件の買取に特化しており、告知義務や法的リスクも熟知したスタッフが対応しています。
お困りの際は、事故物件の買取に強いカンクリ不動産にご相談ください。
経験豊富なスタッフが、告知義務やトラブルリスクをしっかり踏まえたうえで、スムーズな現金化まで丁寧にサポートいたします。
事故物件の告知義務に関するよくある質問
Q.告知義務は何年経てばなくなりますか?
法律上の明確な期間はありません。
ただし、国交省ガイドラインでは賃貸で概ね3年が目安とされています。
Q.自然死や老衰も告知義務がありますか?
原則としてありませんが、死後長期間放置され、特殊清掃を行った場合は告知が必要です。
Q.個人間の売買でも告知義務はありますか?
あります。宅建業者でなくても心理的瑕疵がある事実を知っていた場合、説明責任を問われる可能性があります。
Q.ガイドラインに従えば告知義務違反にはなりませんか?
国交省のガイドラインは判断基準の一つですが、実際には個別ケースでの判断が重要です。ガイドラインを満たしていても、裁判で責任を問われる可能性があります。
まとめ
事故物件を隠して取引することは、後々の損害賠償や裁判リスクに直結します。
「伝えるべきか迷う」場合は、自分で判断せず、不動産の専門家・法律家に相談してください。
リスクを避け、スムーズで安全な取引を行うためにも、誠実な情報開示が最も大切です。